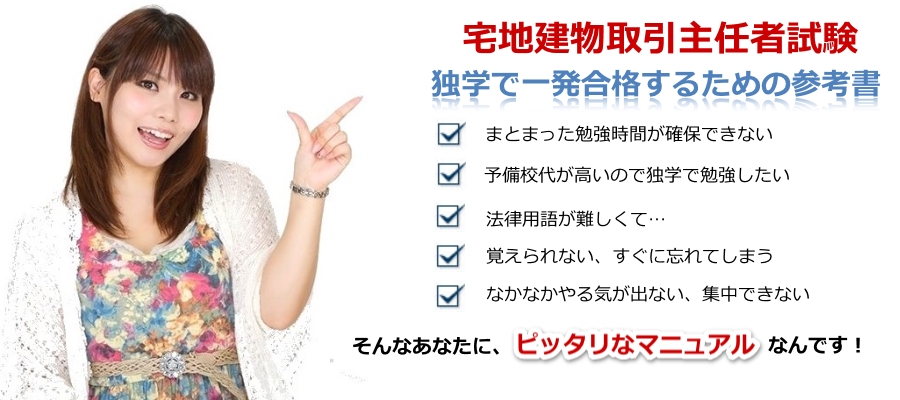管理人の合格体験記 | 宅建独学おすすめ参考書はこれだ!記事一覧
このサイトの管理人です。私は独学で、約3ヶ月の勉強で宅建に一発合格しました。そして、3ヶ月で合格できたのはこのサイトで採り上げている教材のおかげです!…と書きたいところですが、残念ながらそうではありません。私が宅建に合格したのは平成7年。今から20年前の話ですから、まだこのような画期的な教材がなかった頃の話なんです。ですから、何とか合格はできたものの、決して効率よく勉強して合格したわけではありませ...
このサイトの管理人です。私の宅建合格体験記を読んで下さって、ありがとうございます。私は前年、行政書士試験の受験をしたことは前回の体験記に書きましたね。しかし、私はその年の行政書士試験に落ちてしまったのです。正直、自信はありました。でも私の番号がない…現在は行政書士試験もかなり難しい試験となってしまいましたが、その頃の行政書士試験は、正直そこまで難しい試験ではない、とされていました。合格率こそ、今と...
大学はちょうど夏休みに入ったところ。しかも大学の夏休みって長いんですよ。2ヶ月ぐらいはありましたかね。いくらでも勉強時間は費やせる、絶好の時期でした。まあ、大学が始まったとしても、あまり講義には出ない生活を送っていましたが。何が何でも宅建に一発合格してやる!もの凄い気迫で、私は勉強を始めます。まずは民法から。まずは民法から手をつけました。ここは行政書士試験のときにも勉強してますので、それほど苦には...
前回述べたように、私は宅建と行政書士のダブル受験を決意しました。そこで行政書士試験の申込みも済ませ、早速テキストを買ってきました。行政書士は前年受験していたので、テキストは持ってはいたのです。でも新たな気持ちで勉強したかったため、テキストも一新してしまいました。買ってきたテキストは、「早わかり行政書士(久保輝幸)」。私が使っている宅建のテキストと同じ著者の本です。そしてこのテキストがまた分厚い!宅...
宅建の勉強のほうは、宅建業法に入ります。ご存じの通り、宅建業法は宅建試験において最大限の得点源であると同時に、この科目をポロポロ落としていては合格できないというほど重要な科目でもあります。私が受験した当時は16問ぐらいの出題だったでしょうか。現在は出題数が20問に増えており、ますます重要性が増した科目となっています。宅建業法は覚えれば点になる科目です。ですからひたすら覚えていきました。単に覚えてい...
もう試験まで残り1ヶ月余りとなったこの時期。まだ勉強し終わっていない、建築基準法や都市計画法などもどんどん手をつけていきました。もう民法関連や宅建業法は点が取れる自信がありましたから、ひたすら残りの科目を詰め込んでいきます。合格点は毎年変化がありますが、私が受けた年の直近数年間は35点、すなわち7割取れれば合格点を切ることはありませんでした。ですから7割取れればいい、全科目勉強できなくても、民法と...
いよいよ試験本番がやってきました。当時も今と同じ、10月の第3日曜だったと思います。私は試験会場へと足を運びました。指定された自分の席に座り、周りを見渡すと…「うおお、おっさんばっかりやんか!」現在は私もその「おっさん」の仲間入りを果たしているのですが…当時まだ学生だった私は、失礼ながらそんな感想を抱いてしまいました。前年行政書士試験を受験したときは、そのようには感じませんでした。宅建を受ける年齢...
日建学院に着いた私は、机の上に積んであった解答速報を見つけ、1枚もらって家に帰りました。早速自己採点してみます。正解も多いようですが、間違いもソコソコある感じ。そして採点をし終えて、点数を集計してみると…35点。うーん、何とか合格ラインを超えたか?ボーダーライン付近か?まあ大丈夫かな?でもマークミスがあるかもしれない…受けたときの手応えほど悪くない点でしたが、余裕で合格という点でもなく、結局合格発...
さてさて、待ちに待った12月の合格発表。自己採点で35点ありましたので、合格の可能性は高いと思っていました。でも試験は何があるか解らない。合格をこの目で見るまでは…まだネットが発達していない時代です、合格発表もわざわざ発表場所まで見に行きました。どこで合格番号を掲示していたのか、ちょっと記憶に残っていません。20年近く経つと、忘れてしまうものなのですね。私の番号は…ありました!宅建試験に合格してい...
もう宅建には合格したのですから、気分はかなり楽になっていました。でもせっかく行政書士試験も受けたのだから、こちらも受かっておきたい…ついつい欲張ってしまうのが人の情ってもの。法律科目については大丈夫だと思うんですよ。問題は、当時あった小論文のほう。法律の小論文ならまだしも、何かよくわからない一般教養の小論文ですからね。宅建のほうに重点を置いていたこともあって、小論文対策は何もできずに試験に臨むこと...